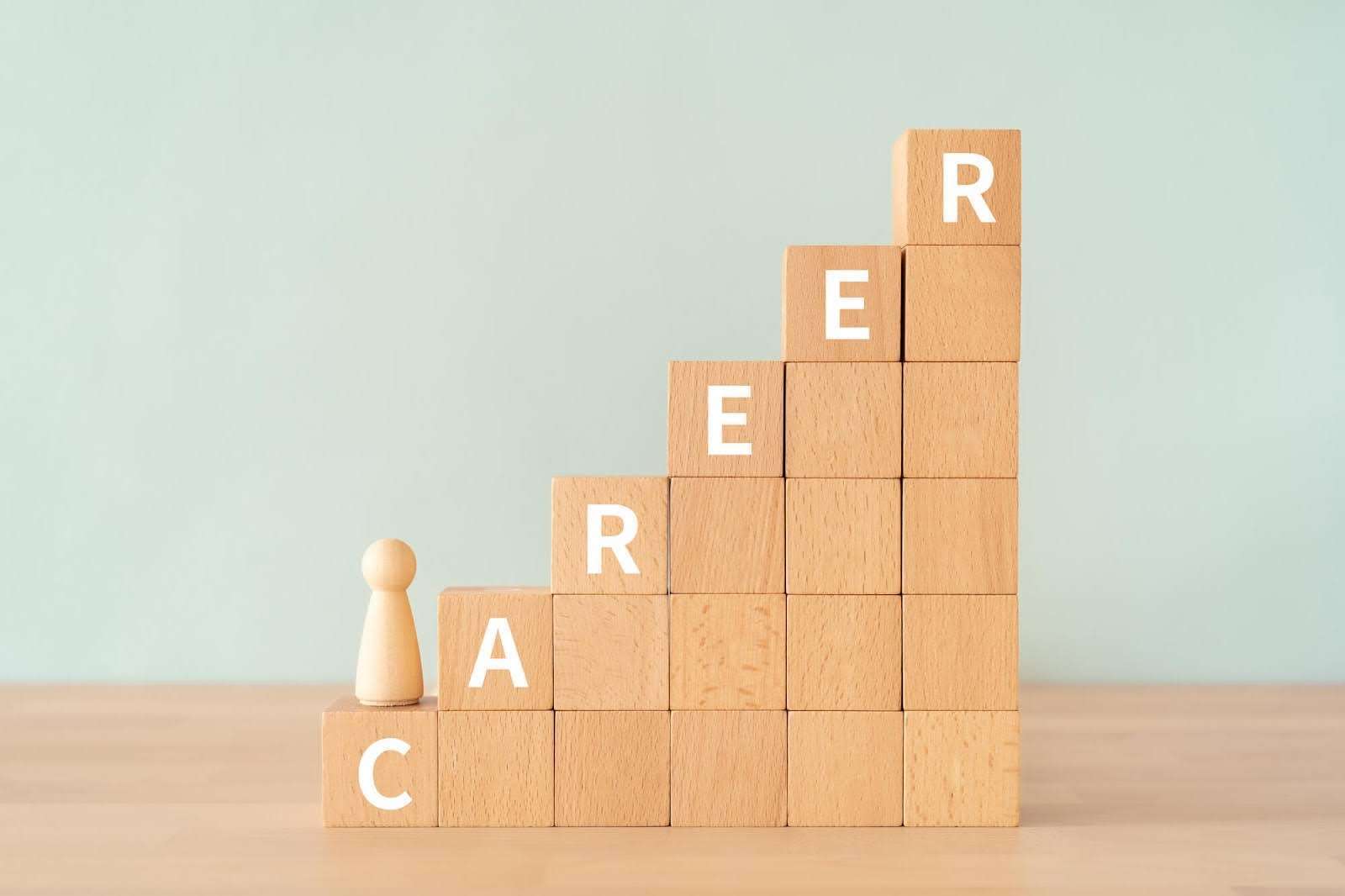高校卒業後に電気工事士として働き始めると、最初に気になるのはやはり「給料の実態」でしょう。初任給の目安は、地域や会社規模によって差がありますが、全国平均ではおおよそ月収20万〜22万円程度が相場とされています。決して高額とは言えないスタートかもしれませんが、ここで重要なのは「その後どう伸ばせるか」です。
実際、電気工事士は資格や現場経験を積み重ねることで年収が大きく変化する職業です。早い段階で国家資格を取得すれば、手当が上乗せされるケースも多く、さらに職長や現場責任者としての役割を任されるようになれば、月収・年収ともに安定的に上昇していきます。
また、建設業界全体で人手不足が続くなか、電気工事士の需要も高まっており、業界全体の賃金水準もじわじわと上昇傾向にあります。給与は年功序列ではなく、個人の技量や資格、働き方によって変わってくるため、自分次第で収入アップを実現しやすい職種とも言えるでしょう。
初任給の相場と市場の追い風

高卒で電気工事士として就職する場合、初任給はどれくらいになるのでしょうか。厚生労働省の調査によれば、高校新卒の技術・技能職種における平均初任給は約20万9千円、建設業界に絞れば約22万4千円が一般的な水準となっています。この金額は、職種別で見ても比較的高い部類に入るといえるでしょう。
さらに注目したいのが、現在の就職市場の状況です。高校新卒者に対する有効求人倍率は全国平均で約3.9倍と、売り手市場が続いています。特に電気工事士をはじめとした技能系職種では、慢性的な人材不足が続いており、未経験者でも採用に前向きな企業が多いのが特徴です。
加えて、公共事業の増加や設備の老朽化による更新需要など、業界自体にも安定したニーズがあります。そのため、入職時点の待遇だけでなく、将来的な昇給やポジションの獲得にも前向きな環境が整ってきているといえるでしょう。
ただし、注意したいのは「会社選び」です。同じ職種であっても、企業の方針や規模、労働条件によって初任給や昇給スピードに大きな差が出ることがあります。求人票の表面上の金額だけではなく、手当の種類や残業代の支給有無、教育制度の有無など、細かい点まで確認することが大切です。
給料が上がる“メカニズム”とは?5つの昇給因子

電気工事士として働きながら給料を上げていくためには、いくつかのポイントがあります。単に年数を重ねれば自動的に昇給するわけではありません。ここでは、収入に影響を与える5つの主要な因子を紹介します。
1つ目は「資格の取得」です。第二種電気工事士を取得していれば現場作業が可能ですが、第一種にステップアップすれば、より大規模な工事に携わることができ、資格手当や責任ある役割に繋がります。さらに電気主任技術者(電験)や施工管理技士などの資格があると、管理職や設計職への道も開けます。
2つ目は「手当の種類と支給条件」。多くの企業では、夜勤手当や現場手当、職長手当などが支給されるため、月収は基本給以上に膨らみます。特に夜間工事や高所作業、出張を伴う業務では手当が厚くなる傾向にあります。
3つ目は「役職やポジションの昇格」です。作業を任されるだけの見習いから、図面を読んで作業指示を出せるレベルに成長すると、職長や現場代理人といった役職に就くことも可能です。責任は増しますが、その分、給与や待遇は大きく改善されます。
4つ目は「扱う案件の規模や内容」です。民間の小規模な工事と比べ、公共施設や大手企業の設備改修工事などは、工程管理や施工精度に求められるレベルが高いため、相応の報酬が支払われやすい傾向にあります。
5つ目は「働き方の柔軟性と実働時間」。時間外勤務や休日出勤の多さは体力的な負担もありますが、残業代や休日手当が適切に支給されていれば、年収ベースでは大きな差となります。逆に、無理な労働が強いられる会社では長く働けないため、バランスも重要です。
このように、電気工事士の給料は「努力次第で上げられる職種」であり、戦略的にキャリアを設計することが将来の収入に直結します。
ステップ別のリアルレンジ
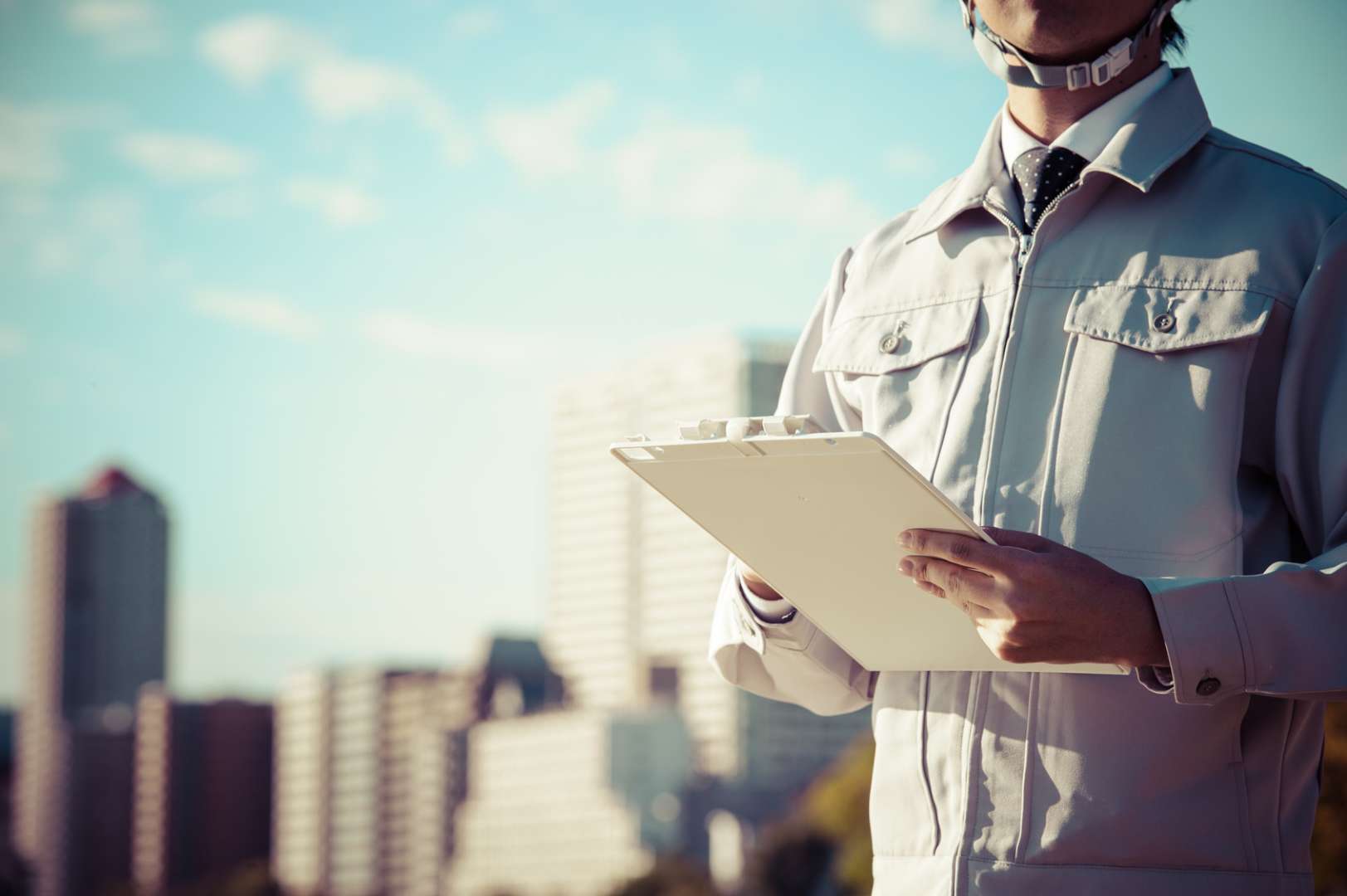
電気工事士として働くうえで、給料がどのように変化していくのか。その成長過程を「年数」ごとのステップで見ていくと、より現実的なキャリア設計が描きやすくなります。
まず、入社1〜3年目の若手期。まだ見習い的な立場で、複雑な作業は先輩のサポートが中心になります。この段階では年収でおおよそ300万〜380万円程度が一般的ですが、資格手当や夜勤などで増えるケースもあります。第二種電気工事士の取得が昇給の第一歩となるため、早めの合格がカギになります。
次に、4〜6年目あたりになると、一人で任される作業が増え、現場のサブリーダー的な役割を担うことも。第一種電気工事士を取得したり、職長補佐として工程管理や材料発注などを任されるようになると、年収は400万〜500万円に届くことも珍しくありません。
そして、7年目以降の中堅期に入ると、現場代理人や職長としての責任ある立場に進む人も出てきます。この段階では、年収が550万〜650万円、場合によっては700万円を超えることもあり得ます。もちろんこれは、単に年数が経てば達成できるわけではなく、資格や対応できる工事の種類、会社の方針や人材育成の仕組みによって左右されるものです。
このように、年収のレンジはあくまで“幅”であり、何を学び、どんな現場で、どのように働くかによって、実際の金額は変わります。自分の将来像と照らし合わせながら、必要な経験やスキルを逆算して積み上げていくことが、安定した収入への近道です。
長時間・繁閑・安全――入社前に必ず確認するポイント
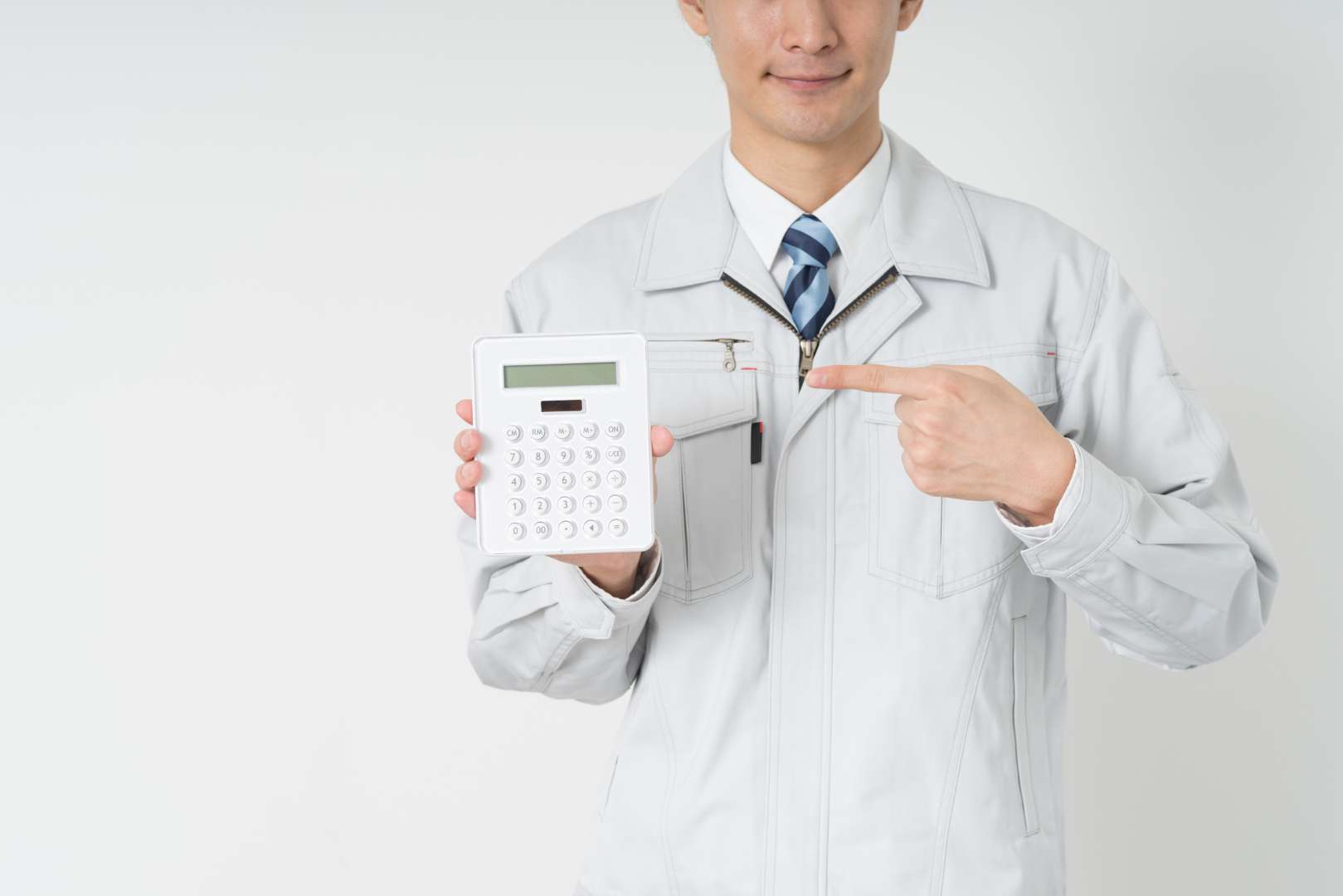
電気工事士は現場での実作業を伴う職業であり、体力や安全への配慮が欠かせません。そのため、給料や資格といった“表の情報”だけでなく、働きやすさや長期的な視点からの“裏の情報”にも目を向けておくことが大切です。
まず注意すべきは「労働時間」と「残業の扱い」です。建設業はどうしても繁閑の差が大きく、繁忙期には早朝出勤や土曜出勤が発生することもあります。問題はその時間が「正当に手当として支払われているかどうか」。求人票の基本給だけを見ていては、その実態が見えてこないことがあります。会社によっては固定残業制やみなし残業を採用しているところもあるため、面接や職場見学の段階で「残業時間」「残業代の支給方法」を明確に確認するようにしましょう。
次に、安全対策です。高所作業や感電のリスクがある電気工事では、フルハーネスの着用や感電防止装備など、企業側の投資が不可欠です。信頼できる会社では、安全教育や講習の機会を定期的に設けたり、作業環境を整備することで、事故のリスクを最小限に抑えようとしています。これらの取り組みが「義務感」ではなく「当たり前」として行われているかが、安心して働ける職場の見極めポイントです。
また、給与や職場環境だけでなく、「資格取得の支援制度」や「作業服・工具の支給」など、働き始めてからのスタートラインをどれだけ整えてくれるかも重要な視点です。多くの優良な企業では、こうした支援制度を通じて社員の定着率を高めています。就職先を選ぶときには、待遇だけでなく“育てる姿勢”があるかどうかを見極めておきましょう。
なお、電気工事士の採用情報は、各企業の採用ページから詳しく確認できます。条件面に加えて、どんな現場を手がけているのか、どのようなチームで働いているのかといった情報を、ぜひ下記リンクからご覧ください。
【採用情報はこちら】
https://www.sunwa-electric.com/recruit
二種合格→現場経験→一種/管理へ――年間スケジュール
電気工事士として収入を上げていくには、資格の取得と現場経験の積み重ねが欠かせません。なかでも、第二種電気工事士の資格は「最初の一歩」として位置づけられています。この資格は学歴や年齢に関係なく誰でも受験できますので、高卒であっても、早めにスケジュールを確認し、着実に準備を進めていくことが大切です。
例年、第二種電気工事士の筆記試験は5月頃に実施され、合格者はその後7月ごろに技能試験を受けます。近年ではCBT(コンピュータ試験)方式も導入されており、申込や試験日程の選択肢が広がっています。一種は少し難易度が上がりますが、現場経験を積んだうえで挑戦することで、施工範囲が広がり、年収アップにもつながります。
また、普通自動車運転免許(できればMT=マニュアル)を在学中に取得しておくこともおすすめです。多くの現場では自動車での移動が必要になるため、免許の有無が就職後の配属や作業内容に大きく影響します。
実務経験が積まれてくると、現場の取りまとめや工程管理といった“管理職的な業務”にも携わるチャンスが出てきます。この段階では、施工管理技士などの資格取得も視野に入ってくるでしょう。
すぐにすべてを達成するのは難しいですが、1年ごとに「何を目標にするか」を定めておくことで、成長の道筋が明確になります。焦らず、確実にステップを踏んでいくことが大切です。
もし、資格取得やキャリアステップについて、具体的な不安や質問がある場合は、企業の採用窓口へ直接問い合わせてみるのも一つの方法です。気になる点があれば、以下のページから気軽に相談してみてください。
【お問い合わせはこちら】